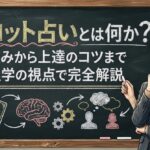「なんでこの人、何も言わないんだろう…」
「なんでも“いいよ”って言われると、逆に困る…」
職場や友人関係で、こんなモヤモヤを感じたことはありませんか?
それ、もしかしたら「遠慮しすぎる人」によるものかもしれません。
一見控えめで優しそうに見えるけれど、実は周囲を疲れさせる原因になっていることもある“過剰な遠慮”。
この記事では、遠慮しすぎる人がなぜ「めんどくさい」と思われがちなのか、そしてどうすれば上手に付き合っていけるのかを、心理的背景から具体的な対処法までわかりやすく解説します。
「わかる!」「それ私かも…」と共感しながら読める内容になっていますので、ぜひ最後まで読んで、よりよい人間関係を築くヒントにしてみてくださいね。
目次
なぜ「遠慮する人」はめんどくさく感じるのか?
本音が見えなくて疲れる
遠慮する人と話していると、「結局どう思っているの?」と感じることがよくあります。
本音を出さず、相手に合わせようとする姿勢は、一見思いやりのように見えます。
しかし、それが続くと相手は「何を考えているのか分からない」というストレスを感じてしまいます。
たとえば、食事に行く時に「どこでもいいよ」と言い続ける人がいたら、選ぶ側は責任を背負わされたように感じます。
それが毎回続くと、「また自分が全部決めないといけないのか」とうんざりしてしまうのです。
本音を言ってくれれば、すれ違いや誤解も減ります。
でも遠慮が強い人は、「自分の意見で相手が嫌な思いをするのでは」と不安になり、本心を抑えてしまいます。
その結果、会話は表面的なものになり、相手にとっては「距離を感じる」「信用できない」といった印象に変わっていくのです。
人間関係では、信頼が大きなカギになります。
遠慮が強すぎると、その信頼が築きにくくなり、「この人、めんどくさいな」と感じさせる原因になるのです。
「気を遣わせる」距離感がしんどい
遠慮する人は、自分が気を遣うだけでなく、周りにも気を遣わせる傾向があります。
「私は大丈夫だから」「気にしないで」と言われても、本当にそうかどうか相手は不安になります。
たとえば、何かを提案したときに「うん、いいと思うよ」と言いつつも表情が微妙な人。
その一言で、「本当にいいのかな?」「無理してるんじゃないかな?」と気になってしまいますよね。
このようなやりとりが重なると、相手は常に「地雷を踏まないように」言葉を選ばなければならなくなります。
気を遣うことが当然になり、心からリラックスして話せなくなってしまいます。
また、遠慮して言いたいことを言わない人がいると、周囲はその人の気持ちを“想像”で補おうとします。
「きっとこう思ってるんだろう」と勝手に気を回し、それが外れるとさらにギクシャクするのです。
結果的に、本人は良かれと思って遠慮しているのに、周りは疲れてしまい、「あの人といるとしんどい」と感じるようになります。
決断を任されがちで責任が重い
遠慮する人は、「あなたに任せるよ」「私はどっちでもいいよ」と言って、決断を相手に委ねることが多くなります。
これは一見すると柔軟な姿勢のようにも思えますが、実は相手に負担をかけています。
たとえば、旅行の計画を立てるとき。
「行き先は?」「ホテルは?」「何食べたい?」と聞いても、「何でもいいよ」が返ってくる。
結局、すべてを決めるのは自分。
そして、もし相手が楽しめなかった場合、「私が決めたから責任を感じる…」とモヤモヤするのです。
遠慮して決断を避ける人は、相手を思ってそうしているつもりかもしれません。
でも実際は、相手に責任を押しつけることにもなってしまいます。
「一緒に決めてほしい」「意見を出してほしい」という気持ちが伝わらず、相手の中には「この人、めんどくさいな」という感情が少しずつ積もっていきます。
社交辞令が多くて不自然
遠慮が強い人は、場の空気を壊さないように、つい社交辞令を多用しがちです。
「すごいですね」「私なんてまだまだです」「また今度ご一緒しましょう」など、一見丁寧に見える言葉も、使いすぎると不自然に聞こえてしまいます。
特に、日本では“建前”の文化があるため、どこまでが本心なのか分からない場面が多くあります。
それが重なると、「この人って何を考えてるんだろう?」「信用していいのかな?」と疑問を持たれやすくなります。
また、社交辞令が多すぎると、会話のリアルさや親密さが失われます。
深い話ができず、いつも表面的なやりとりになってしまうため、「なんだか疲れるな」と感じられてしまうのです。
社交辞令を完全にやめる必要はありません。
でも、相手に合わせすぎず、少しずつでも自分の本音を出すことが大切です。
感謝されにくく損した気分になる
遠慮する人は、「迷惑をかけたくない」という気持ちから、誰にも頼らずに自分だけで何とかしようとすることが多いです。
その結果、周囲の人からは「何もしてないように見える」「助けがいがない」と思われてしまうこともあります。
また、自分からお願いをしない分、周りの人が何かしてくれたときも、感謝の言葉が少なかったり、そっけなく見えたりすることがあります。
そうなると、手を差し伸べた側は「なんか損した気分だな」と感じやすくなります。
遠慮が美徳とされる場面もありますが、行き過ぎると「冷たい人」「かわいげがない」と思われてしまうこともあります。
結果的に、相手の好意をうまく受け取れず、関係が深まるチャンスを逃してしまうのです。
遠慮する姿勢がめんどくさく感じられるのは、「伝わらない」ことで誤解が生まれ、心の距離が広がっていくからなのです。
遠慮しすぎる人の心理を知ろう
断るのが怖い「いい人」タイプ
遠慮しすぎる人の中には、「断ること=悪いこと」と考えている人がいます。
特に、周りから「いい人」と思われたい気持ちが強い人ほど、その傾向があります。
たとえば、頼まれごとを断ると「冷たい人だと思われるのでは?」と心配になってしまいます。
そのため、本当は無理をしているのに「大丈夫ですよ」と引き受けてしまいがちです。
結果、自分が疲れたり、周囲に余計な気を遣わせたりすることになります。
この「いい人」タイプは、人に嫌われたくない、争いたくないという気持ちが強いのが特徴です。
断る勇気を持つことよりも、人間関係の波風を立てないことを優先します。
そのため、常に自分を抑えてしまい、遠慮の度が過ぎてしまうのです。
実は、人に好かれるためには「自分の意思を持つこと」も大切です。
どんなに優しくても、自分の意見を持たない人は信頼されにくくなります。
相手も「この人に頼んで大丈夫かな?」と不安になってしまうのです。
遠慮ばかりしていると、自分も周囲も疲れてしまいます。
「いい人」でいることと、「言うべきことを伝える人」でいることは、両立できます。
自己肯定感が低くて自信がない
遠慮しすぎる人の心理には、「自分なんて…」という自己否定の感情が隠れていることがあります。
自信がないため、「自分の意見を言っても意味がない」「どうせ誰にも聞いてもらえない」と考えてしまうのです。
こういった人は、自分の価値を低く見てしまう傾向があります。
そのため、会話の中でも「でも…」「どうせ…」というネガティブな言葉が多くなり、相手にも暗い印象を与えてしまいます。
また、自信がない人ほど、相手の顔色をうかがう癖があります。
「今の言い方まずかったかな」「あの人怒ってないかな」と常に不安を感じているため、積極的に話すことができません。
その結果、会話も曖昧になり、余計に遠慮してしまうのです。
自己肯定感を高めるには、まず「自分の気持ちを認める」ことが大切です。
自分の感じたこと、考えたことに「それでいい」と言えるようになると、自然と自信もついてきます。
遠慮が減ることで、人間関係もよりスムーズになります。
相手の評価を過剰に気にしてしまう
「嫌われたくない」「変な人だと思われたくない」という気持ちから、遠慮が強くなってしまう人もいます。
このタイプは、他人の目や評価を過剰に気にしてしまい、自分の行動をセーブしてしまいます。
例えば、会議で意見を求められたとき、本当は言いたいことがあるのに「間違っていたら恥ずかしい」と思って黙ってしまう。
友人に誘われたけど、断ったら嫌われるかもしれないと考えて、無理して予定を合わせてしまう。
このように、相手の反応を想像して行動を決めることが多くなります。
しかし、これは自分自身の気持ちを抑え込むことにつながり、結果的にストレスがたまりやすくなります。
人間関係は「自分」と「相手」のバランスで成り立っています。
相手の評価ばかりを気にしていると、自分の存在感が薄れてしまい、「本当のあなた」が見えなくなってしまいます。
大切なのは、相手に合わせるだけでなく、「自分らしさ」を出すことです。
評価はコントロールできませんが、自分の気持ちは大事にできます。
争いを避ける「平和主義」
遠慮しがちな人には、「争いごとが苦手」という人が多くいます。
とにかく空気を壊したくない、誰かが不快になるようなことは言いたくない。
そういった気持ちから、言いたいことを我慢してしまうのです。
たとえば、仕事でトラブルが起きても、「自分のせいじゃない」と分かっていても口をつぐんでしまう。
家族や友人との会話で嫌なことを言われても、笑ってごまかしてしまう。
争いを避ける姿勢は、一見すると大人の対応のように見えます。
ですが、それが度を越すと「自分の気持ちを無視する生き方」になってしまいます。
平和を守ることは素晴らしいですが、自分の意見や感情を押し殺してまで成り立つ関係は、長続きしません。
我慢の限界が来たときに、突然爆発したり、フェードアウトしてしまうケースもあります。
争い=悪いことではありません。
本音でぶつかり合うことが、かえって信頼関係を深めることもあるのです。
自分の気持ちに鈍感なケースも
意外かもしれませんが、遠慮が多い人の中には「自分が何を感じているのか分からない」人もいます。
つまり、自分の本心に気づいていないのです。
これは、長年自分を抑えて生きてきた人によく見られる傾向です。
自分の感情よりも「どうすれば相手が喜ぶか」「嫌われないか」を優先してきたため、いつの間にか自分の気持ちに鈍感になってしまったのです。
例えば、レストランで「何食べたい?」と聞かれても、答えが出てこない。
本当に何が食べたいのか、自分でも分からない。
これは小さなことのようですが、実はとても深刻です。
自分の気持ちに気づけないと、他人との関係も築きにくくなります。
相手に合わせるだけの会話はすぐに限界が来ますし、信頼関係も築けません。
まずは、「自分が何を感じているのか」に意識を向けてみることが大切です。
日記を書く、心に浮かんだ言葉をメモするなど、少しずつ「自分を知る」習慣を取り入れていくと、自然と遠慮も減っていきます。
めんどくさいと思わずに接するコツ
相手に安心感を与える言葉を使う
遠慮しがちな人は、「自分がどう思われているか」に敏感です。
だからこそ、相手から安心できる言葉をもらえると、心がほどけていきます。
たとえば、「何でも言って大丈夫だよ」「遠慮しなくていいよ」といった言葉。
このようなひと言があるだけで、「自分の意見を言っても大丈夫なんだ」と感じてもらいやすくなります。
また、無理に本音を引き出そうとせず、「○○だったらどう思う?」と選択肢を与える聞き方も有効です。
プレッシャーを与えずに話しやすい雰囲気を作ることで、相手も徐々に心を開いてくれる可能性が高くなります。
「気を遣ってほしくない」という気持ちは、優しさで伝えることが大切です。
きつい言い方やイライラを見せてしまうと、相手はもっと萎縮してしまいます。
相手のペースに合わせつつ、少しずつ「安心していいよ」という空気を作っていくことがポイントです。
相手が遠慮しすぎていると感じたときこそ、「自分はあなたを受け入れているよ」というメッセージを言葉にすることが、関係性を深める第一歩になります。
本音を聞き出す「余白の会話術」
遠慮がちな人に「本音を言ってほしい」と思っても、直接「どう思ってるの?」と聞くと、かえって引かれてしまうことがあります。
そんな時に有効なのが、「余白を作る会話」です。
たとえば、質問したあとに無言の時間を少しだけ作ってみる。
人は沈黙があると、つい何かを話したくなります。
この“間”が、相手の本音を引き出すきっかけになるのです。
また、「○○って思う人もいるけど、どう?」といった柔らかい聞き方も効果的です。
選択肢を示しながら聞くと、「私はこう思うかも」と話しやすくなります。
さらに、「あなたの意見、聞けてうれしいよ」と一言添えると、相手は「言ってよかった」と安心します。
それが次の会話にもつながり、遠慮の壁を少しずつ崩すことができるのです。
遠慮する人には、「聞く側の姿勢」がとても重要です。
詰め寄らず、急がず、余白のある聞き方を心がけましょう。
意図を明確に伝えてみる
遠慮する人は、相手の意図が曖昧だと「自分がどうすればいいのか分からない」と不安になります。
だからこそ、こちらの意図を明確に伝えることが、相手の安心感につながります。
たとえば、「あなたの意見を大切にしたいから、聞かせてほしい」と目的を先に伝えると、相手も安心して答えやすくなります。
ただ「どう思う?」と聞かれるよりも、理由がわかっていた方が答えやすいのです。
また、お願いをするときも「気を遣わなくて大丈夫だから」「無理なら断ってもいいよ」と前置きすることで、相手の不安を軽減できます。
遠慮しがちな人は、「言わないことで傷つかずに済む」と思っていることがあります。
しかし、相手が明確な意図を持っていると分かれば、「言っても大丈夫かも」と感じるようになります。
相手に配慮することと、遠慮させないことは両立できます。
こちらの誠意や目的をしっかり伝えることで、相手の心のハードルを下げることができるのです。
遠慮しすぎる相手を否定しない
相手が遠慮ばかりしていると、「はっきりしてよ!」「もっと言ってよ!」とイライラしてしまうことがあります。
でも、そこで相手を責めたり否定したりすると、ますます心を閉ざしてしまいます。
遠慮の背景には、不安やトラウマ、過去の経験が関係していることも多いです。
だからこそ、相手の態度に腹を立てるのではなく、「この人には何か事情があるのかもしれない」と受け止めることが大切です。
たとえば、「いつも気を遣ってくれてありがとう」「話しにくいときは無理しなくていいからね」といった言葉があるだけで、相手の心はずいぶん軽くなります。
また、「自分も昔は言えなかったことがあってね」と共感を示すことで、相手も少しずつ安心し、距離が縮まることがあります。
大切なのは、「遠慮する=悪いこと」と決めつけずに、相手のペースを尊重することです。
否定せず、寄り添う姿勢が、信頼関係を育てていきます。
自分の境界線もきちんと伝える
相手に遠慮ばかりされていると、こちらが気を遣いすぎて疲れてしまうこともあります。
そんなときは、自分の「限界」や「思っていること」を丁寧に伝えることも大切です。
たとえば、「何でも任せてもらえるのはうれしいけど、一緒に決められたらもっと助かるよ」と伝えてみましょう。
攻撃的にならず、相手の行動を尊重しながら、自分の思いも伝えることで、関係がより対等になります。
また、「今日は少し疲れてるから、静かに過ごしたい」といったように、自分の状態を正直に伝えることもポイントです。
遠慮しすぎる人は、相手が疲れていることにも気づかないことがあるので、しっかり伝えることで誤解を防げます。
自分の気持ちや立場をはっきり伝えることは、わがままではありません。
むしろ、お互いが無理をしない関係を築くためには必要なことです。
遠慮する人にばかり合わせていると、いつか関係が破綻してしまう可能性もあります。
だからこそ、「自分を守るための伝え方」も大切にしていきましょう。
自分が「遠慮しすぎる人」になっていないかチェック!
YES/NOでわかる自己診断テスト
まずは、自分がどれくらい「遠慮しすぎているか」をチェックしてみましょう。
以下の10個の質問にYESかNOで答えてみてください。
| 質問 | YES / NO |
|---|---|
| 相手の顔色を常に気にしてしまう | |
| 本当は嫌だけど断れずに引き受けることが多い | |
| 自分の意見を言うのが苦手 | |
| 「どっちでもいいよ」が口ぐせになっている | |
| 相手を怒らせるのが怖くて本音を隠すことがある | |
| 何かを頼まれると断った後に罪悪感を感じる | |
| 誰かに迷惑をかけるくらいなら自分が我慢したほうがいいと思う | |
| 自分の感情をうまく言葉にできない | |
| 相手に気を遣いすぎて疲れることがよくある | |
| 本当は助けてほしいのに「大丈夫」と言ってしまう |
YESが6つ以上ある人は、かなり遠慮が強く出ている傾向があります。
無意識のうちに自分を抑え込んでいる可能性があるので、自分の気持ちにしっかり向き合っていくことが大切です。
まずは「自分が遠慮してしまう場面」に気づくことが第一歩。
気づけるようになると、少しずつ改善が始まります。
日常会話でのNGパターン
遠慮が強すぎると、会話の中でも無意識に相手に気を遣いすぎてしまい、逆に「話しにくい人」と思われてしまうことがあります。
たとえば、以下のような言い回しは、相手を困らせる原因になります。
-
「どこでもいいよ」→ 相手が決めなければいけないプレッシャーになる
-
「何でも大丈夫」→ 本音が見えなくて不安になる
-
「私なんて…」→ 自信がなさすぎて話が盛り下がる
-
「別にいいよ」→ 無関心と誤解される可能性がある
-
「そんなことないです」→ 褒められた時に否定すると、相手も戸惑う
このような言い回しを繰り返していると、「会話のキャッチボール」が成り立ちません。
結果的に、「何を考えているのか分からない人」「話が盛り上がらない人」という印象を持たれてしまうことがあります。
言葉は自分の気持ちを伝える大切な手段。
遠慮しすぎずに、自分の意見や感情を少しずつ言葉にしていくことが大切です。
相手が気を遣いすぎる原因を探る
もし「自分と話すと相手が気を遣っているように見える」と感じたら、それは自分の遠慮しすぎが原因かもしれません。
たとえば、話を振られても「何でもいいです」と返すことが多いと、相手は「どうすればいいの?」と困ってしまいます。
あるいは、褒められても「いえいえ、そんなことないです」と全否定すると、相手は「褒めたのに受け取ってもらえなかった」と残念に感じることがあります。
遠慮しすぎて「反応が薄い」「感情が伝わらない」と思われると、相手はどんどん気を遣うようになります。
「何を言えば正解なのか分からない」と感じさせてしまうのです。
つまり、相手が気を遣っているように見えるのは、自分が「遠慮しすぎている」サインでもあります。
そのことに気づくだけでも、会話のスタイルを少しずつ変えることができます。
「遠慮」と「配慮」は違うという意識
「遠慮」と「配慮」は似ているようで、実は大きく違います。
遠慮は「自分を抑えること」。
配慮は「相手を思いやること」です。
遠慮ばかりしていると、「本当の自分」を出すことができなくなります。
それに対して配慮は、自分の意見を持ちながらも、相手の立場や気持ちを考えるバランスの取れた行動です。
たとえば、誰かと一緒にお店を選ぶとき。
遠慮は「どこでもいいよ」と言うこと。
配慮は「私は和食が好きだけど、○○さんは何が食べたい?」と聞くこと。
遠慮は時に、相手に負担を与えてしまいます。
でも、配慮はお互いを思いやる関係を作ります。
自分が「遠慮してるな」と感じたときは、それを「配慮」に変えられないか考えてみてください。
ちょっとした意識の違いが、人間関係を大きく変えるきっかけになります。
小さな一歩から「言える自分」へ
遠慮しすぎる自分を変えたいと思っても、いきなり大胆になろうとすると疲れてしまいます。
だからこそ、「小さな一歩」が大切です。
たとえば、レストランで「これが食べたい」と言ってみる。
友達に「この日は都合が悪い」と素直に伝えてみる。
職場で「もう少し時間が必要です」と相談してみる。
こうした小さな挑戦を積み重ねることで、「言っても大丈夫だった」という成功体験が生まれます。
それが少しずつ、自信につながっていくのです。
遠慮を手放すことは、自分を大切にすることでもあります。
「本音を伝えること=わがまま」ではありません。
むしろ、相手との信頼関係を深めるための大切なステップです。
一歩ずつでいいので、「言える自分」になることを意識してみましょう。
良い関係を築くためにできること
遠慮を手放す練習法
「遠慮するのがクセになっている…」という人は、少しずつ練習していくことで変わっていくことができます。
大切なのは、いきなり完璧に変わろうとせず、段階的に“遠慮を手放す”習慣をつけることです。
まずは、自分の本音に気づく練習から始めましょう。
「今、どうしたい?」「本当はどう思っている?」と、心の中で自分に問いかけてみるだけでもOKです。
そして、その気持ちを少しずつ言葉にしてみましょう。
たとえば、レストランで「今日はこれが食べたいな」と言ってみる。
誰かに「この日はちょっと都合が悪い」と素直に伝えてみる。
こういった小さなアクションが、自分の気持ちを尊重する練習になります。
さらにおすすめなのが、「気持ちメモ」や「日記」。
一日の終わりに「今日、言いたかったこと」「我慢したこと」を書き出してみると、自分のパターンが見えてきます。
遠慮をやめることは、わがままになることではありません。
「自分の思いも大事にしながら、相手と向き合う」ための大切な一歩です。
伝え方を少し工夫するだけで変わる
本音を伝えるとき、「どう言うか」がとても大切です。
伝え方を少し工夫するだけで、相手に与える印象は大きく変わります。
たとえば、ただ「いやだ」と言うのではなく、「私は○○のほうが安心するな」とポジティブに伝える。
「できません」ではなく、「○○だったらお手伝いできるよ」と代案を出す。
このように、柔らかい表現や前向きな言い回しを意識すると、相手にも受け入れられやすくなります。
また、「私は〜と思うんだけど、どうかな?」というクッション言葉を使うことで、遠慮せずに自分の意見を伝えつつ、相手を尊重する姿勢も見せられます。
本音を伝える=ぶつかる、ではありません。
伝え方を工夫すれば、お互いが気持ちよく話せるようになります。
少しずつ、言葉の選び方に意識を向けてみましょう。
距離感のバランスを意識する
良い人間関係を築くためには、「近すぎず、遠すぎず」の距離感が大切です。
遠慮が強すぎると、相手との距離が遠くなりすぎてしまい、関係が深まりません。
逆に、何でもかんでも言いすぎると、相手が引いてしまうこともあります。
たとえば、仕事仲間とは適度な敬語と丁寧さをキープしつつ、自分の意見もしっかり伝える。
プライベートの友人には、遠慮しすぎず、でも相手の気持ちをちゃんと考える。
このように、相手との関係性によって「ちょうどいい距離」を意識することが大切です。
また、「この人とはまだ距離があるな」と感じたら、いきなり踏み込まず、少しずつ関係を深めていくよう心がけましょう。
焦らず、自然なタイミングで本音を出せるようにすると、関係も無理なく続いていきます。
距離感の取り方は、人それぞれ。
だからこそ、相手の反応を見ながら、バランスをとる力が求められるのです。
遠慮しすぎる相手とも対等になるには?
遠慮がちな人と関わると、つい「こっちが気を遣わなきゃ」と思いがちです。
でも、良い関係を築くには、お互いが「対等」であることが大切です。
まず意識したいのは、「相手に頼ることも大切」という考え方。
遠慮する人は、頼られることに慣れていないことが多いですが、実は「頼られること」によって自信を持つきっかけになることもあります。
たとえば、「これお願いしてもいい?」とあえて小さなことを頼んでみる。
「○○してくれて助かったよ」と感謝を伝える。
これだけで、相手の中で「自分も役に立てる存在なんだ」と思えるようになっていきます。
また、自分が我慢してまで相手に合わせるのではなく、「お互いが譲り合える関係」を目指すことも大切です。
時には率直に「一緒に決められたらうれしいな」と伝えることで、相手の遠慮も少しずつほぐれていきます。
みんなが心地よくなる関係性の作り方
遠慮しすぎない、でも相手を思いやる。
そんな“ちょうどいい関係”を築くには、以下の3つのポイントを意識すると良いでしょう。
-
気持ちをオープンにする
「今日はこうしたいな」「今ちょっと疲れてる」など、自分の気持ちを素直に伝えることから始めましょう。 -
相手の言葉を否定しない
遠慮がちな人の言葉に対しても、「そう思うんだね」「なるほど」と受け止める姿勢があると、安心感が生まれます。 -
感謝と承認の言葉を忘れない
「言ってくれてありがとう」「助かったよ」というひと言は、関係を温かくする魔法のような言葉です。
人と人との関係は、言葉と気持ちのキャッチボールでできています。
一方的にならないように、相手の気持ちにも自分の気持ちにも、同じくらい耳を傾けることが大切です。
「心地よい関係」は、自然と長続きします。
遠慮しすぎず、無理しすぎず、お互いが安心できる関係を一緒に育てていきましょう。
まとめ
遠慮しすぎる人との関係は、時に「めんどくさい」と感じられてしまうことがあります。
しかし、その背景には不安や自己否定、相手への気遣いといった深い心理があることも事実です。
この記事では、なぜ遠慮しすぎる人が周囲に負担を与えてしまうのか、そしてどうすればより良い関係を築けるのかを、具体的に解説してきました。
まずは相手の心理を理解すること。
そして、こちらから安心感を与えるような言葉や態度を心がけることが、信頼関係を深める第一歩です。
一方で、自分自身が遠慮しすぎていないかを振り返ることも大切です。
「言いたいことを言う勇気」「相手に頼ること」「自分の本音を伝えること」。
これらは人間関係を豊かにするための、大切なスキルです。
遠慮は決して悪いものではありません。
ただし、過剰な遠慮はお互いの関係を歪めてしまうこともあります。
「配慮」と「遠慮」を上手に使い分けて、みんなが心地よく過ごせる関係を目指していきましょう。