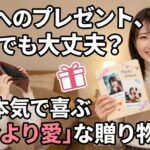「また決められないの?」「早くしてよ!」
そんなふうに感じること、ありませんか?
優柔不断な人と関わっていると、物事が前に進まずイライラしてしまうこともありますよね。
でも、そのイライラの正体を知って対処法を身につければ、もっと心穏やかに過ごせるようになります。
この記事では、優柔不断な人にイライラしてしまう理由や心理、うまく付き合うための具体的な方法まで、分かりやすく解説しています。
ストレスを減らして、より良い人間関係を築くヒントを探してみませんか?
目次
なぜ優柔不断な人にイライラするのか?心理的な理由を解説
判断を先延ばしにされると不安が募る
優柔不断な人と接していると、何かを決める場面で「どうしようかな…」と長時間悩まれることがあります。
一見、丁寧に考えているようにも見えますが、付き合っている側としては「いつ決めるの?」と不安になってしまいます。
特に、仕事や予定、約束事など、時間に関係することが絡む場面ではこの不安が強くなります。
「早く決めてくれないと、こっちの予定が立てられない」と感じると、自然とストレスが溜まってしまいます。
これは「不確実性への不安」と呼ばれる心理反応です。
人は、結果がはっきりしないことに対して本能的にストレスを感じます。
つまり、優柔不断な人の判断保留が、無意識に私たちの「安心」を脅かしているのです。
また、自分一人で決められない人に対して、「なんで自分ばかりが気を使わないといけないのか」と不満を感じることもあります。
こういった積み重ねが、「イライラ」の正体になっていくのです。
責任を取らない姿勢にモヤモヤする
優柔不断な人は、決断することで何かしらの「責任」を負うことを避けたい気持ちが強い場合があります。
「Aを選んだ結果、失敗したら自分のせいだ」と思うと、怖くなって決められなくなるのです。
すると、自然と他人に決定を委ねたり、「どっちでもいいよ」と責任逃れをするような言動が増えてきます。
これが一緒にいる側からすると、「こっちに押しつけられてる」と感じてしまい、モヤモヤが募っていきます。
責任を取らない=相手に負担をかけている、という意識がないため、悪気がないのもやっかいなところです。
しかし、人間関係ではバランスがとても大切です。
一方だけがいつも決断して、もう一方がそれに乗っかる構図が続くと、確実にストレスがたまります。
その小さな「モヤモヤ」が積み重なって、「イライラ」や「もう関わりたくない」といった感情へとつながってしまうのです。
自分の意見を言わないことで対話が成立しない
優柔不断な人は、「どう思う?」と聞いても「うーん…わからない」「どっちでもいいかな」などと返してくることが多いです。
こちらとしては会話を進めたいのに、いつも返答があいまいだと、対話そのものが成立しません。
人間関係は、キャッチボールのようなものです。
一方が投げても、もう一方が返してくれなければ成立しません。
優柔不断な人はこの「返す」部分が極端に苦手であるため、会話が一方通行になりやすいのです。
それが続くと、「自分の意見がないの?」「どうして言ってくれないの?」と感じ、徐々に不満がたまります。
その不満が「話していても面白くない」「一緒にいても疲れる」という感情につながるのです。
結果として、会話のリズムが崩れ、コミュニケーションがストレス源になってしまいます。
これが、イライラする大きな原因の一つです。
一緒にいると物事が進まないストレス
優柔不断な人と一緒に何かを決める場面では、あらゆることがスローペースになります。
例えば「ランチどこに行く?」というシンプルな話でも、「どこでもいいよ」と言われてしまい、結局決めるのは自分。
そのうえ「本当にここで良かったかな…」と不安げにされると、決めた側としても疲れてしまいます。
こういった場面が日常的に続くと、「この人といると前に進まない」と強く感じるようになります。
時間も労力も奪われるように思えてくるため、「一緒にいると疲れる」という印象が生まれます。
スムーズに行動できないことで、自分のペースが崩れてしまうのも大きなストレス要因です。
これは、時間や効率を大切にする現代人にとって、特に大きな不満に感じやすい部分でしょう。
無意識に相手をコントロールしたくなる心理
優柔不断な相手に対して、「もういいからこっちで決めるよ!」と強く出たくなる場面はありませんか?
これは、自分のイライラを解消するために、無意識に相手を「コントロールしよう」としている心理です。
しかし、人間関係において相手をコントロールしようとすると、反発や不満が生まれやすくなります。
相手の反応が鈍かったり、決断力がないことに対して、自分がイライラしてしまい、余計に関係が悪化する…という悪循環に陥りがちです。
つまり、相手の優柔不断な性格と、それに対する自分のコントロール欲がぶつかってしまっているのです。
この心理に気づかないまま放置すると、イライラはどんどん増えていきます。
自分が相手に「どうなってほしい」と強く望むほど、現実とのギャップに悩み、ストレスが大きくなるのです。

優柔不断な人の特徴とその裏にある本音
他人に嫌われたくないという気持ち
優柔不断な人の中には、「他人にどう思われるか」をとても気にするタイプが多くいます。
自分の意見をはっきり言って、もし相手に否定されたらどうしよう。
選んだ選択肢で相手が不満に思ったらどうしよう。
そんな不安から、自分の気持ちを抑えてしまうのです。
特に日本の文化では、「和を乱さない」ことが美徳とされてきた背景があります。
そのため、空気を読みすぎて自分の意思を見せられなくなるという傾向も少なくありません。
「相手に合わせたほうが無難」と考えるクセがついてしまうと、ますます自分の本心を伝えられなくなります。
その結果、「どっちでもいいよ」「任せるよ」という言葉が口癖になってしまうのです。
けれど、これは決していい加減なのではありません。
むしろ、「相手を傷つけたくない」「嫌われたくない」という思いやりの裏返しとも言えます。
それでも、相手からすれば「意見がなくて頼りない」と感じてしまうのが難しいところですね。
自信のなさから決断が怖くなる
優柔不断な人は、自分に対して自信を持っていない場合が多いです。
「自分の選んだことが正しいかどうか自信がない」
「間違っていたらどうしよう」
そんな気持ちが強いため、決断するのがとても怖くなってしまいます。
これは、過去の経験や育ってきた環境が影響していることもあります。
たとえば、子どもの頃に親や先生から「なんでそんなこと選んだの!」と怒られた経験があると、それがトラウマになっていることもあります。
その経験が頭をよぎることで、選ぶことそのものに恐怖を感じてしまうのです。
また、自分の意見を否定され続けた経験があると、「どうせ私が決めても…」とネガティブになり、どんどん自信を失ってしまいます。
このように、本人の中では「決めたくない」のではなく、「決めるのが怖い」という気持ちが強く働いています。
理解を深めることで、少し見方が変わるかもしれませんね。
選択肢が多すぎて迷ってしまう
現代はあらゆるものが「選べる時代」です。
食べ物ひとつとっても、コンビニに行けば何十種類もおにぎりが並んでいます。
ネットで買い物をすれば、同じ商品が価格もデザインもバラバラで選び放題です。
この「選択肢の多さ」が、優柔不断な人にとっては最大の敵になります。
選ぶという行為は、実は脳にとってかなりのエネルギーを使います。
特に選択肢が多いと、「どれが一番良いのか」「失敗しないのはどれか」と考えるうちに、どんどん混乱してしまうのです。
心理学ではこれを「選択のパラドックス」と呼びます。
選択肢が多すぎると、かえって人は選べなくなるのです。
優柔不断な人は、この状態に陥りやすく、「決めきれない」という苦しさを抱えています。
本人にとっては「選びたいけど、選べない」というジレンマであり、そこに周囲からのプレッシャーが加わると、さらに混乱してしまうのです。
過去の失敗がトラウマになっている
誰でも一度や二度、選んだ結果うまくいかなかったという経験はあると思います。
でも、その経験が深く心に残ってしまい、トラウマとなっている人もいます。
たとえば、「友達と遊びに行く場所を決めたけど、思ったよりつまらなかった」と言われた経験。
「仕事で自分が進めた案が失敗して、上司に責められた」など、過去の小さな失敗が尾を引いているのです。
このような経験があると、「また失敗するかもしれない」という恐れから、どんどん決断することにブレーキがかかります。
「自分が決めたら、また悪い結果になるかもしれない」
そう考えると、何を選ぶにも怖くて進めなくなるのです。
その恐怖が、表面的には「優柔不断」という形で現れていることがあるのです。
過去の出来事を思い返してみると、その人がなぜ迷いやすいのか、少し理解できるようになるかもしれません。
周囲に「正解」を求める傾向がある
優柔不断な人は、自分で答えを出すことが苦手なだけでなく、他人に「どっちがいいと思う?」と聞くことが多い傾向があります。
これは、正解を自分の中で見つけられないため、他人の意見を頼りにしようとする行動です。
しかし、正解というのは多くの場合、人それぞれです。
「こっちが良い」と言っても、相手は別の意見かもしれません。
それに直面すると、さらに迷いが深まり、結局どれも決められなくなってしまうのです。
また、「周りの目」を気にするタイプでもあります。
他人にどう思われるかを気にするあまり、自分の判断ではなく「みんなが選びそうなもの」に流されてしまいます。
結果として、いつまでも結論を出せないループに入ってしまうのです。
こうした特徴を理解することで、「なんでこの人はいつも迷うんだろう?」という疑問が少し解けてきますね。
イライラを爆発させないための心の整え方
相手の性格を理解する努力をする
まず、イライラを抑えるためには「相手の性格を理解しよう」とする姿勢がとても大切です。
優柔不断な人は、決してあなたを困らせたいと思って行動しているわけではありません。
多くの場合は「自分がどうしたらいいか分からない」「失敗したくない」「相手に迷惑をかけたくない」という気持ちがベースにあるのです。
この背景を知るだけでも、相手を見る目が少し変わってきます。
たとえば「また決められないの?」と思う代わりに、「この人、決めるのが不安なんだな」と考えることができるようになります。
理解はすべての第一歩です。
相手の弱さや不安を知ることで、感情のコントロールがしやすくなります。
もちろん、理解したからといってすぐにストレスがなくなるわけではありません。
しかし、「なぜそうなるのか」を知っていると、少なくとも感情の爆発を防ぐことにはつながります。
相手も完璧ではない。
そう思えるだけで、少し心がやわらぐのです。
自分の感情に名前をつけてみる
イライラを感じたとき、「あーもうムカつく!」と一気に爆発してしまうことってありますよね。
でも、その前に一度立ち止まって「今、自分はどんな気持ちなんだろう?」と内面に目を向けてみてください。
これは「感情ラベリング」と呼ばれる心理テクニックで、自分の感情に名前をつけることで心が落ち着く効果があります。
たとえば、「イライラしている」「不安になっている」「疲れている」「がっかりしている」といったように具体的に表現してみましょう。
感情を言語化することで、脳はその感情に支配されにくくなります。
「イライラしているけど、実は自分が焦っていたんだな」と気づければ、対処方法も変わってくるはずです。
また、相手に対して「イライラしているから距離を取りたい」と冷静に伝えることもできるようになります。
感情をコントロールする力は、自分の内面を知るところから始まるのです。
距離を取ることで冷静になれる
感情が高ぶってきたときは、無理にその場で何かを決めようとしないことが大切です。
イライラしながら話を続けても、うまくいかないことがほとんどです。
そんなときは、物理的・心理的に少し距離をとってみましょう。
たとえば、「少しだけ一人になりたい」と伝えて席を外す。
あるいは「今日はちょっと疲れているから、また明日話そう」と伝えて一度保留にする。
これだけでも、自分の気持ちが落ち着き、冷静さを取り戻せるようになります。
人間は感情が高ぶると、論理的な判断ができなくなります。
「なんでいつもこうなの!」という怒りに任せた発言は、相手との関係を悪化させるリスクが高いです。
だからこそ、少し引く勇気を持つことが、心の余裕を保つコツなのです。
「離れる=逃げる」ではありません。
よりよい関係を築くための、冷却時間だと考えましょう。
呼吸を整えるマインドフルネスの活用
イライラが爆発しそうなとき、すぐにできる心のケア方法として「呼吸を整える」ことがあります。
これはマインドフルネスと呼ばれる方法の一部で、意識的に呼吸に集中することで心を落ち着かせる効果があります。
やり方はとてもシンプルです。
背筋を伸ばして座り、目を閉じます。
そして「吸って…吐いて…」というリズムで、ゆっくり深呼吸を繰り返します。
このとき、頭の中で考え事が浮かんできても、「あ、今イライラしてるな」と気づいて、また呼吸に意識を戻します。
これを1分〜3分行うだけでも、感情の波が少しずつ穏やかになっていくのを感じられるはずです。
イライラの渦中にあるときこそ、まずは「立ち止まる」ことが必要です。
マインドフルネスは習慣化することで、感情のコントロールがしやすくなります。
優柔不断な人と向き合うためにも、自分の心の状態を整える練習はとても有効なのです。
「期待しすぎない」ことを意識する
イライラの正体は、「相手に対する期待」が裏切られたときに強く表れます。
「もっとはっきりしてくれると思ってたのに」
「そろそろ決めてくれると思ってたのに」
そんなふうに、無意識に期待してしまっているのです。
でも、優柔不断な人は「今までそうだったように、これからもすぐには変わらない」可能性が高いです。
だからこそ、「期待しすぎない」という意識を持つことで、自分の心のダメージを減らすことができます。
「この人は、すぐには決められない人なんだ」
そう認めることで、こちらの心の準備もできるようになります。
そして、「あまり多くを求めない」ことで、余計なイライラが減っていくのです。
もちろん、全く期待しないというのは難しいかもしれません。
でも、少しだけハードルを下げるだけで、自分の心は驚くほど軽くなるのです。

スムーズな会話を引き出すテクニック
二択で質問してみる
優柔不断な人に「どうしたい?」と聞いても、「うーん…どっちでもいい」と返ってくることが多いです。
そんな時は、選択肢を絞ってあげることが効果的です。
例えば、「今日のランチ、和食と洋食どっちがいい?」と聞くと、相手は選びやすくなります。
この方法は、心理学でも「選択肢の限定」として知られており、迷いやすい人の意思決定を助けるテクニックです。
なぜ二択が効果的なのかというと、脳への負担が減るからです。
10個の中から1つを選ぶのは大変ですが、2つなら直感でも選びやすくなります。
さらに、二択で選ばせることで「自分で選んだ」という満足感も得やすくなるのです。
これは、仕事の場面やプライベートの予定調整など、さまざまな場面で使える便利な方法です。
選択肢を一緒に提示することで、相手とのコミュニケーションもスムーズになります。
決定の期限を明確に伝える
「いつでもいいよ」と言ってしまうと、優柔不断な人はいつまでも決められないまま迷い続けます。
そのため、決断を求めるときは「〇時までに決めよう」「今日中に考えてね」など、はっきりと期限を伝えることが効果的です。
期限があることで、相手は「いつまでに決めなきゃいけない」と意識を持つようになります。
これは心理的に「締切効果」とも言われ、行動を促すのにとても有効です。
もちろん、プレッシャーを与えすぎるのは逆効果なので、「無理に急がなくていいけど、15時には一度決めたいな」など、柔らかい言い方を心がけましょう。
期限があることで相手も気持ちの整理がつきやすくなり、判断への一歩を踏み出しやすくなります。
特に職場やグループ活動など、時間に制約がある場面ではこの方法は非常に役立ちます。
共感から入ることで安心感を与える
優柔不断な人がなかなか決断できないのは、「自分の判断が否定されるかも」という不安を抱えているからです。
そのため、まずは共感することで相手に安心感を与えることが大切です。
たとえば、「迷うよね、それ分かるよ」と一言添えるだけでも、相手の心はぐっとほぐれます。
「どっちが正しいか分からなくなるよね」「私も前に同じことで迷ったことあるよ」と伝えれば、相手は自分だけが迷っているのではないと感じられます。
安心できる環境があることで、人は本来の判断力を発揮しやすくなります。
緊張しているときよりも、リラックスしているときの方が選択しやすいのと同じです。
会話を始めるときには、まず「理解しようとする姿勢」を見せること。
それが、相手との信頼関係を深め、スムーズなコミュニケーションへとつながります。
小さな選択から慣れさせる
優柔不断な人にとって、いきなり大きな決断をするのはとてもハードルが高いものです。
そんなときは、まず「小さな選択」から始めるのが効果的です。
たとえば、「飲み物はお茶とコーヒーどっちがいい?」
「席はこっちとあっち、どっちにする?」
このように、日常の些細な選択を繰り返すことで、決断に対する抵抗感を少しずつ減らしていくことができます。
選ぶことに慣れてくると、次第に「自分で決める」という自信もついてきます。
これは、自己効力感(セルフエフィカシー)を高める練習でもあります。
一歩ずつでも「自分で決めていいんだ」と感じられるようになれば、よりスムーズな会話や意思疎通ができるようになっていきます。
焦らず、小さなステップから始めることが、長い目で見たときに大きな成果を生むのです。
決めるメリットを言葉にする
優柔不断な人は、「どちらかを選ぶ」ことのリスクばかりを考えてしまいがちです。
「間違ったらどうしよう」「後悔するかも」と不安が強く、なかなか一歩を踏み出せません。
そんなときは、「決めたらどんな良いことがあるか」を具体的に伝えてあげるのが効果的です。
たとえば、「早く決めたら、この後ゆっくりできるよ」
「今決めれば、みんなが動きやすくなるね」など、行動のメリットを前向きな言葉で伝えましょう。
ポジティブな未来を想像させることで、不安よりも期待の方が大きくなります。
これは「リフレーミング」と呼ばれる心理テクニックで、物事の見方を変えることで心の反応を変える方法です。
相手の中に「決めても大丈夫かも」という感覚を育てることが、優柔不断を和らげる第一歩になります。
決めることの「怖さ」ではなく「良さ」を伝えることが、スムーズな会話と関係性づくりのカギになります。
優柔不断な人との付き合い方を見直そう
役割分担をはっきり決める
優柔不断な人との関係でストレスを減らすには、あらかじめ「どの部分を誰が決めるか」を明確にするのが効果的です。
例えば、旅行の計画を立てるなら「宿泊先は私が決めるから、食事の場所はお願いね」というように、役割分担をするのです。
これは、一方がすべてを決めて疲れてしまう事態を防ぐ方法です。
優柔不断な人も「自分が決めるべき範囲」がはっきりしていれば、そこに集中して考えやすくなります。
また、自分が任されたという意識が芽生えることで、責任感も育ちます。
重要なのは、「決めることが苦手でも、全部を任せるわけじゃない」と伝えること。
相手の負担を軽くしつつ、自分のストレスも減らすために、うまくタスクを振り分ける工夫をしていきましょう。
こうした方法は、夫婦や同僚、友達関係など、さまざまな人間関係で使える実践的なテクニックです。
自分のペースを大事にする
優柔不断な人と接していると、どうしても自分が相手に合わせる機会が増えてしまいます。
その結果、「なんでいつも自分ばかりが我慢してるの?」という気持ちになりがちです。
この状態を避けるためには、まず「自分のペースを大切にする」という意識が必要です。
「相手が迷っていても、自分は自分のペースで行動しよう」
「今日は疲れているから、相手の相談に全部付き合うのはやめよう」
こうした「自分軸」を持つことが、心の安定につながります。
無理に合わせようとすると、知らず知らずのうちにストレスがたまり、爆発してしまう可能性があります。
そうなる前に、自分の感情や体調を優先する時間を確保することが大切です。
「付き合う=すべてを受け入れる」ではありません。
お互いの距離感をうまく保つことが、長く付き合っていくコツなのです。
伝えるべきことはハッキリ言う
優柔不断な人との関係でありがちなのが、「察してくれるだろう」と思って自分の本音を飲み込んでしまうことです。
しかし、これは関係をこじらせる原因になります。
相手は迷いやすいぶん、こちらの意図や希望を読み取る力が弱いこともあります。
だからこそ、「自分はこうしたいと思っているよ」と、具体的に言葉で伝えることが大切です。
たとえば、「私は早く決めたいから、10分以内に決めてくれると助かる」
「どっちでもいいって言われると困るから、何かしら意見を出してくれると嬉しい」など。
やわらかい言い方で構いません。
でも、ハッキリ伝えることで相手にも意識の変化が生まれます。
言わなければ伝わらない。
これを心に留めて、少しずつでも対話の質を高めていきましょう。
無理に変えようとしない姿勢が大事
つい「もっとしっかりしてよ」「早く決めてよ」と言いたくなる気持ち、よくわかります。
ですが、優柔不断な人の性格は、長年の思考パターンや不安からくるもので、そう簡単には変わりません。
無理に変えようとすると、相手もプレッシャーを感じてさらに動けなくなることがあります。
そうなると、お互いにとって苦しい関係になってしまいます。
そこで大切なのが、「変えるのではなく、うまく付き合う」ことです。
相手のペースを尊重しながら、自分の心の余裕も確保する。
そのバランスを取ることで、長く良い関係を築くことができます。
人はみんな、それぞれのペースでしか成長できません。
焦らず、少しずつ変化を待つ。
そのくらいの距離感が、ちょうどいいのかもしれません。
時には関係性そのものを考え直す
どんなに工夫しても、どうしても相手にイライラしてしまう。
一緒にいると疲れてしまう。
そんなふうに感じることが続くようであれば、無理に関係を続ける必要はありません。
人間関係は、相手との相性も大切です。
優柔不断な人にとっては、自分のペースを尊重してくれる人が必要かもしれませんし、あなたにとっては、もっとテンポよく物事を決められる人との方が心地よいかもしれません。
もちろん、すぐに距離を置く必要はありませんが、「この関係は本当に自分にとってプラスかどうか」を見つめ直すことも大事です。
自分の心が常に消耗しているような関係は、長い目で見て健全とは言えません。
大切なのは、自分を犠牲にしないこと。
相手を変えようとする前に、自分にとってベストな距離感や関わり方を見つけていきましょう。
まとめ
優柔不断な人に対してイライラしてしまうのは、決してあなただけではありません。
相手がなかなか決断しないことで、自分のペースが乱され、ストレスを感じるのはとても自然な反応です。
しかし、その背後には「自信のなさ」「失敗への恐れ」「他人への気遣い」といった、相手なりの理由や背景があることも忘れてはいけません。
この記事では、相手の心理的な特徴を理解しながら、実際に使えるコミュニケーションの工夫や、自分自身の心の整え方、関係の見直し方まで幅広く紹介しました。
イライラするのは悪いことではなく、ただ「気づき」のサインでもあります。
自分の中にある期待や負担を見つめ直すチャンスだと考えてみてください。
そして、「変えようとする」のではなく、「うまく付き合う」工夫を重ねていくことが、心地よい人間関係の第一歩です。
無理せず、自分のペースも大事にしながら、相手との関係を少しずつ整えていきましょう。