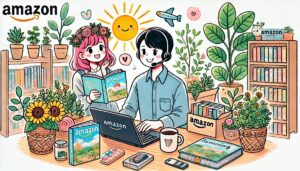「夫婦で生活保護を受けることは可能なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
仕事が見つからない、病気で働けない、年金だけでは生活できない——さまざまな理由で生活に困ることは誰にでも起こりえます。
この記事では、 夫婦で生活保護を受けるための条件や支給額、申請手順をわかりやすく解説 します。
また、受給中の注意点や、自立するための方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
夫婦世帯の生活保護費はいくらもらえる?
生活扶助費の計算方法
生活保護の支給額は、国が定める「最低生活費」から世帯の収入を差し引いた金額になります。
最低生活費は、家族構成や居住地域によって異なり、夫婦二人世帯の場合、おおよそ 13万円〜15万円程度 が基準となります。
最低生活費は以下の3つの要素で構成されます。
| 項目 | 内容 | 夫婦二人世帯の目安 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 衣食住などの生活費 | 8万〜10万円 |
| 住宅扶助 | 家賃や共益費(上限あり) | 4万〜7万円 |
| その他の扶助 | 医療・介護・教育扶助など | 必要に応じて支給 |
例えば、東京23区の夫婦世帯の場合、生活扶助が約10万円、住宅扶助の上限が6万円程度となるため、合計 16万円前後 になることが多いです。
一方、地方では住宅扶助の上限が低いため、全体の支給額も少なくなる傾向があります。
また、 夫婦のどちらかに障害がある場合や、高齢である場合は加算 がつくことがあります。
そのため、実際の支給額は個別の事情によって変わります。
住宅扶助はどこまで支給される?
住宅扶助(家賃補助)は、家賃が自己負担できない場合に支給されますが、 上限額が決まっている ため、高額な賃貸には住めません。
| 地域 | 夫婦世帯の住宅扶助上限額 |
|---|---|
| 東京都23区 | 約6万円〜7万円 |
| 大阪市 | 約5万円〜6万円 |
| 名古屋市 | 約5万円 |
| 地方都市 | 約4万円〜5万円 |
例えば、東京都で月7万円の賃貸に住んでいる場合、上限が6万円なら、1万円は自己負担する必要があります。
逆に、家賃が5万円なら全額補助されます。
また、住宅扶助は 賃貸のみ対象 であり、持ち家の場合は対象外となります。
ただし、 固定資産税や修繕費が特例で認められる場合 もあるため、福祉事務所に相談してみましょう。
医療扶助や介護扶助の内容とは?
生活保護世帯は 医療費が全額支給 されるため、病院にかかる際の 自己負担は0円 になります(医療扶助)。
これは、生活保護を受けている間は 健康保険に加入する必要がない ためです。
また、 高齢の夫婦や障害を持つ場合、介護扶助も支給 されます。
これにより、介護サービスを無料で受けることができます。
【医療扶助の対象例】
✅ 診察料
✅ 入院費
✅ 手術費
✅ 薬代
✅ 検査費用
【介護扶助の対象例】
✅ デイサービス利用
✅ 訪問介護
✅ 介護用ベッド・車椅子の貸与
✅ 介護施設の利用
ただし、 自由診療(美容整形など)や高額な入院個室費用 は対象外になるため、注意が必要です。
冬季加算やその他の特別扶助とは?
寒冷地に住んでいる場合、冬季加算が支給されることがあります。
これは、暖房費がかかる地域向けに支給されるものです。
例えば、北海道や東北地方では 1ヶ月あたり1万円前後 の加算がつくことがあります。
また、特別な事情がある場合には、以下のような特別扶助が支給されることもあります。
| 特別扶助の種類 | 内容 |
|---|---|
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 |
| 葬祭扶助 | 葬儀費用の一部負担 |
| 義務教育扶助 | 学用品・給食費の補助 |
| 障害者加算 | 障害の程度に応じた追加支給 |
これらの特別扶助は 必要に応じて支給 されるため、該当する場合は申請しましょう。
地域による生活保護費の違い
生活保護費は地域によって異なり、大都市ほど高額になります。
これは、物価や家賃が違うためです。
| 地域区分 | 夫婦世帯の最低生活費(目安) |
|---|---|
| 東京都(特別区) | 約16万円 |
| 大阪・名古屋などの大都市 | 約15万円 |
| 地方都市(県庁所在地など) | 約14万円 |
| 郊外・地方 | 約13万円 |
例えば、東京都では家賃補助が高いため、総額で16万円程度になりますが、地方では14万円程度になることが多いです。
これは、地域ごとに設定されている「級地区分」によるものです。
【級地区分の例】
- 1級地(東京23区・横浜・大阪など)→支給額が高い
- 2級地(地方都市)→中間
- 3級地(農村部・過疎地域)→支給額が低い
住んでいる場所によって支給額が違うため、 引っ越しを検討する際は福祉事務所に相談 するのがベストです。

夫婦で生活保護を受けるための申請手順
生活保護の申請窓口と必要書類
生活保護の申請は 住んでいる地域の福祉事務所(生活保護課) で行います。
事前に電話で相談することもできますが、原則として 直接窓口で申請する必要があります。
申請に必要な主な書類
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 生活保護申請書 | 窓口で配布される公式の申請書 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、保険証など |
| 収入証明書 | 給与明細、年金通知書、失業保険証明など |
| 預金通帳の写し | 直近の残高が分かるもの |
| 賃貸契約書(持ち家の場合は固定資産税証明書) | 住宅扶助の審査に必要 |
| 医師の診断書(必要な場合) | 病気や障害がある場合 |
自治体によって追加で求められる書類があるため、申請前に福祉事務所で確認しておきましょう。
申請の流れと審査期間の目安
生活保護の申請は 以下の流れ で進みます。
-
福祉事務所に相談
- 収入や資産状況を説明し、申請が可能か確認。
- 「事前相談」として面談が行われることもある。
-
必要書類を準備して申請
- 生活保護申請書を記入し、必要書類を提出。
- この時点で申請が正式に受理される。
-
福祉事務所による調査
- 家庭訪問が行われ、生活状況の確認。
- 預貯金や資産の有無、親族の扶養可能性を調査。
-
審査・決定(通常2週間〜1ヶ月程度)
- 生活保護の可否が決定し、通知が送られる。
- 受給が決定すれば、申請月の分から支給開始。
審査期間中に 収入の変動がある場合は速やかに報告 することが重要です。
申請が却下される主な理由とは?
生活保護の申請が却下される理由には、以下のようなものがあります。
-
最低生活費を上回る収入がある
→ 夫婦の収入合計が支給基準を超えている場合、対象外となる。 -
預貯金や資産が一定額以上ある
→ 一定額以上の貯金があると、「それを先に使うように」と指導される。 -
親族から扶養が受けられると判断された
→ 親や子どもが扶養可能と判断された場合、申請が通らないこともある。 -
働けるのに働こうとしていない
→ 就労可能な場合、仕事を探すよう指導されることがある。
審査に納得できない場合は、 不服申し立て(審査請求) を行うことも可能です。
生活保護受給までの生活費はどうする?
申請後、支給が決定するまでの間は 生活費の工面が必要 です。以下のような方法を活用できます。
- 生活福祉資金貸付制度(一時的な生活費の貸付)
- 社会福祉協議会の支援(食糧支援や日用品の提供)
- 親族や友人からの一時的な援助(返済不要の援助なら問題なし)
生活に困窮している場合、福祉事務所に相談すれば 「緊急支援」 を受けられることもあります。
申請が通らなかった場合の対処法
申請が却下された場合、以下のような対応が考えられます。
-
不服申し立て(審査請求)を行う
- 生活保護法に基づき、却下理由に納得できない場合は「審査請求」が可能。
-
NPOや支援団体に相談する
- 生活困窮者を支援する団体に相談し、別のサポートを受ける。
-
別の支援制度を活用する
- 生活保護以外の支援制度(住宅確保給付金など)を活用する。
申請が通らなかった場合でも、 別の方法で支援を受ける道はある ため、諦めずに相談を続けましょう。
夫婦で生活保護を受ける際の注意点
収入の変動があった場合の報告義務
生活保護を受給中でも、 収入が発生した場合は必ず福祉事務所に報告 しなければなりません。
これは、生活保護の支給額が「最低生活費から収入を差し引いた額」で決定されるためです。
報告が必要な収入の例
✅ 給与(パート・アルバイト含む)
✅ 年金(障害年金・老齢年金など)
✅ 失業手当・労災給付金
✅ 親族からの仕送り
✅ 遺産相続・贈与
【報告のタイミング】
収入があった場合は、 毎月決まった期日までに「収入申告書」を提出 します。
申告を怠ると 不正受給とみなされる可能性 があるため、注意が必要です。
旅行や贅沢な支出はできる?
生活保護を受給中でも、 最低限の娯楽や旅行は可能 ですが、常識の範囲内で行うことが求められます。
✅ 可能な支出の例
- 近場の温泉旅行(格安プラン)
- 月1回程度の外食
- 無料イベントへの参加
❌ 問題視される可能性がある支出
- 高級ホテルや海外旅行
- ブランド品や高額な趣味(高級車、ゴルフなど)
- ギャンブル(パチンコ・競馬など)
生活保護は「最低限の生活を保障する制度」 なので、贅沢が過ぎると福祉事務所から注意を受けることがあります。
就労指導を受ける可能性とは?
夫婦のどちらか、または両方が 働ける年齢・健康状態にある場合 は、福祉事務所から 就労指導 を受けることがあります。
就労指導の内容
- 求職活動の指導(ハローワークへの登録)
- 短時間のアルバイト・パートの推奨
- 職業訓練の受講(無料で受けられる場合もあり)
働く意思がある場合 は、収入が増えることで生活保護からの自立が可能になります。
しかし、 「働けるのに働かない」と判断された場合 は、生活保護の打ち切りや減額の対象となることもあります。
不正受給とみなされるケース
不正受給とは、本来受け取るべきでない人が 虚偽の申告をして生活保護を受けること を指します。
不正受給が発覚すると、 支給された金額を返還する義務 があり、場合によっては 詐欺罪 に問われることもあります。
✅ 不正受給とみなされるケース
- 収入を隠していた場合(パート・アルバイト収入を報告しない)
- 預貯金を過少申告した場合(隠し口座が発覚)
- 親族からの仕送りを隠した場合
- 同居人がいるのに単身世帯と偽った場合
「少しならバレないだろう」と思っても、福祉事務所は 銀行口座の調査や雇用記録の照会 を行うため、 発覚する可能性が高い です。
生活保護を受けながらできる仕事は?
生活保護を受けながらでも 一定の収入を得ることは可能 です。
収入がある場合は、その分生活保護費が減額される仕組みですが、「勤労控除」という制度があるため、 収入のすべてが差し引かれるわけではありません。
✅ 生活保護受給中にできる仕事の例
- 短時間のパート・アルバイト
- 在宅ワーク(ライティング、データ入力など)
- 障害者向けの就労支援プログラム
💡 ポイント
- 「働いた分だけ保護費が減る」のではなく、一部は控除されるため 就労するほど手元のお金は増える。
- 在宅ワークなら体力的な負担が少ない ので、病気がある場合でも可能な場合がある。
働くことにより 生活保護からの自立を目指せる ため、少しでも収入を得る手段を考えるのはメリットがあります。

生活保護を受けながら自立を目指すには?
就労支援制度の活用方法
生活保護を受けている人が 仕事を見つけて自立するための支援制度 があります。
これらを活用することで、無理なく生活保護を抜け出すことが可能です。
✅ 活用できる就労支援制度
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| ハローワークの職業訓練 | 無料で職業スキルを学べる(介護・IT・事務など) |
| 就労準備支援事業 | 生活保護受給者向けの仕事探しサポート |
| 自立支援プログラム | 福祉事務所が紹介する職業相談・研修制度 |
| 障害者向け就労支援 | 障害がある人のための軽作業・リモートワーク支援 |
生活保護を抜け出すためのステップ
生活保護を卒業するには、 徐々に収入を増やし、支出をコントロールすること が重要です。
🔹 STEP1:収入を増やす
- 短時間のアルバイト・パートから始める
- 在宅ワークや軽作業で無理なく稼ぐ
- 職業訓練を受けてスキルアップ
🔹 STEP2:支出を管理する
- 家計簿をつけて無駄な出費を減らす
- 固定費(家賃・光熱費)を見直す
- 節約できる部分を見つける
🔹 STEP3:貯金を始める
- 生活保護を卒業する前に、少しずつ貯金を作る
- いざという時の生活費を確保する
🔹 STEP4:生活保護を卒業する
- 収入が最低生活費を超えたら、福祉事務所に報告
- 生活保護を卒業して、自立した生活へ
貯金や資産形成は可能?
生活保護を受けながらの貯金は 一定額までなら可能 ですが、 多額の貯金は認められません。
💰 貯金が認められるケース
✅ 収入の一部を貯める(少額なら問題なし)
✅ 目的がある貯金(子どもの学費・就職準備費など)
❌ 認められないケース
🚫 数十万円以上の貯金
🚫 株式投資や資産運用
💡 ポイント
貯金が増えた場合は 福祉事務所に相談すれば、例外的に認められることもある。
夫婦で支え合う生活設計の考え方
夫婦で生活保護を受ける場合、 どちらかが働けるなら少しでも収入を得る ことで、早く自立が可能になります。
✅ 夫婦の役割分担を考える
- 夫が働き、妻が家計管理を担当
- 妻がパートで働き、夫が自宅で副業をする
- 夫婦で協力して就労支援を受ける
生活保護は 一時的な支援 であり、「卒業すること」が目標になります。
夫婦で協力しながら、少しずつ生活を立て直すことが大切です。
生活保護を卒業した人の体験談
🎤 Aさん(50代・元生活保護受給者)
「最初はどうしても生活保護から抜け出せないと思っていました。
でも、ハローワークで職業訓練を受けて、事務職の仕事に就くことができました。
最初は時給1000円のパートでしたが、半年後には正社員になれました。
生活保護を受けていたころよりも、自由にお金が使えるようになり、精神的にも安定しました。」
🎤 Bさん(60代・夫婦で生活保護を受給)
「夫婦で生活保護を受けていましたが、夫がシルバー人材センターで仕事を始めました。
収入が増えたことで、少しずつ生活保護の金額が減り、2年後には卒業できました。
生活保護があったおかげで、一度立ち直ることができたので感謝しています。」
まとめ
✅ 夫婦で生活保護を受けるには、収入や資産の条件を満たす必要がある
✅ 支給額は地域によって異なり、夫婦二人世帯で月13万〜16万円程度が目安
✅ 生活保護を受けるには福祉事務所での申請が必要で、調査・審査を経て支給が決定
✅ 収入が増えた場合は報告が必要で、無申告は不正受給のリスクがある
✅ 就労支援を活用しながら、少しずつ自立を目指すことが重要